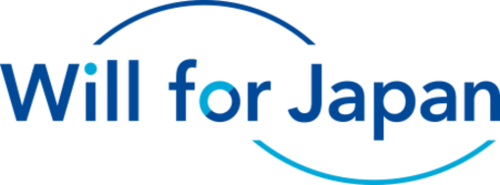研究や教育への遺贈寄付。社会課題を生み出さないための大学の取り組みとは/東京大学

国立大学法人 東京大学
2027年に創設150年を迎える東京大学。「世界の公共性に奉仕する大学」という理念のもと、法・行政・科学・医学・産業・経済・文化・教育など、多様な専門領域で活躍する人材を輩出しながら、世界水準の研究・教育に力を注いできました。大学ならではの多様な使い道と、確かな信頼で選ばれる寄付先として、さらに寄付金を持続的に活用する新たな仕組みづくりに挑戦する東京大学で、遺贈寄付を担当されている堺飛鳥さんと平野尚也さんにお話を伺いました。(取材日:2024年5月31日)

平野 尚也さん(写真右)
大阪大学文学部卒業、東京大学大学院総合文化研究科修了。民間企業営業職、国際協力NGOファンドレイザー等を経て国立大学ファンドレイザーに。
2022年より現職。承継寄付診断士1級。
堺 飛鳥さん(写真左)
東京大学経済学部卒業、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科修了。外資系メーカー・広告代理店等の勤務を経て家族の仕事の都合で北京に帯同。
2020年より現職。準認定ファンドレイザー。承継寄付診断士1級。
目次:
1. 「故人の想いを叶えたい」というご家族に寄り添って
___まずは、遺贈寄付に取り組まれたきっかけと時期からお伺いできますか?
堺)2004年の大学の法人化の後に寄付部門が立ち上がり、以来、遺贈寄付も受け付けてきました。以前も相続財産からの寄付は年に1、2件のご相談があり、対応していたのですが、本格的に取り組み始めたのはここ3年ぐらいです。相談件数が少しずつ増える中、遺贈寄付に取り組む必要性を感じていたものの人員不足でなかなか手が回らなかったところ、人員拡充によって遺贈寄付に関心のあるメンバーが入職し、新しいことをやろうと行動したことが本格化の第一歩となりました。
平野)記録を見てみると東京大学基金が最初に遺言による寄付をいただいたのが2016年となっています。その頃は寄付のお申し出があったら対応をするという受け身の姿勢であったのではないかと思いますが、こちらから積極的に情報提供をしていくようになったのがここ数年のことで、2022年にはパンフレットやホームページも分かりやすくリニューアルしました。
___本格的に取り組まれて以降、反響はいかがですか?
平野)そうですね、お問合せや資料請求の数で言うと、2021年度に30件を超え、パンフレットを改訂した2022年度には100件以上に伸びました。「遺言書を書きたい」といった具体的なお問合せに限っても、年々右肩上がりに増えており、今年度(2024年度)は過去最高に達しそうな状況です。関心の高まりを肌で感じています。
___これまでの中で、特に印象深かったケースはありますか。
平野)やはり遺言書を書いていただく段階からお話を聞けたケースは特に印象に残っていますね。私はもともとNPO法人で働いていたのですが、NPOにご寄付をくださる方の場合、例えば紛争などで困っている人たちを助けたいという想いを専門家に託したいということが寄付の動機になることが多いです。一方、大学への寄付の場合、例えば、ご自身が当校の卒業生であったり、東大病院で治療を受けたことがあったり、お世話になった大学に恩返しがしたいと、ご自身の経験にもとづいて寄付したいと思ってくださる方が多いように感じます。

平野)そのような動機の違いを反映して、NPOの場合には、寄付者の方が団体側の話を聞いて、活動内容を理解して寄付をするという流れになるのですが、大学に寄付される方は、ご自身のことをよくお話してくださいます。自分はこういう経験をしてきたから、こんな想いがあるから東京大学に寄付を託したいとお話してくださる方が多いです。寄付者のみなさまがこれまで生きてこられた人生のお話をたくさんお聞きできるので、どのケースも本当に印象深いです。
___堺さんはいかがですか?
堺)私は、入職して最初に担当した案件がとても印象に残っています。故人の方が卒業生で、ご遺族から連絡をいただいたケースです。故人の方は生前、東大病院にかかっておられたこともあり、大学にお世話になったので遺産の一部を寄付したいというご希望をお持ちでした。ただ、闘病中に遺言書を残すことまではできなかったそうで、ご本人の生前の希望を叶えるためにどうしたらいいか、というお問い合わせをいただきました。
出来る限りご本人の希望に沿った形でのご寄付を実現できるよう、ご家族に生前故人がどんなことに関心をお持ちで、どんな学生生活を送っていたかなどお話を伺いました。その中で、学生時代に所属されていたテニスサークルのこと、ご友人が今も当校で教鞭をとっていることなどをお聞きし、後進育成の観点から、テニスコートの補修や学生支援など、ご本人だったら興味を持たれたのではないかという使途をいくつかご提案させていただきました。ご家族も、そういう使い方なら本人も喜ぶと思います、と納得してご寄付くださいました。故人の方の想いはもちろん、ご遺族の方のお気持ちに寄り添うにはどうすればいいのかということを学ばせていただいたケースでした。
___遺贈寄付の意義を感じるような場面はありますか。
堺)今お話ししたケースのように、相続財産からの寄付をいただく場合、執行時、ご遺族はまだ故人を亡くされた悲しみの中にいます。悲しみを抱えながらも、故人の想いを何とか実現してあげたいと奮闘されています。私たちは、その想いにしっかり寄り添いながら対応しなければいけないといつも肝に銘じています。
ご遺族の方も納得できるご提案ができれば、故人の生きた証を形にすることができるので、そのことがご遺族の慰めにもなるのではないかと思います。故人の想いを叶えたいというご遺族のお気持ちに応えることができることが、遺贈寄付の大きな意義ではないかと感じています。
2. 寄付者の想いを未来につなぐ信頼と継続の仕組み
____活動する中で大切にされているのはどんなことですか。
堺)やはり、想いに寄り添うことと、信頼関係を築くことではないかと思います。例えば、お元気な方から「遺言書を書きました」というご連絡をいただいた場合、可能な限り、生前からのご寄付もお願いするようにしています。というのは、大きな額を託していただく以上、ご自身の寄付が実際どのような活動に使われるのかを、ぜひご自身の目で確認していただきたいからです。実際の活動を体感していただくことが目的なので、1回限りでも、100円や1000円のご寄付でも構いません。そうすることで、私たちの活動への理解と信頼を深めていただき、より安心感をもって寄付を託していただけたら嬉しく思います。
平野)ご本人やご家族に納得いただける形で寄付を活用することを大切にしています。使途指定がある場合は、そのお気持ちに添って、指定された研究・教育に活用できるよう調整に努めます。また、使途指定がない場合には、大学の財政基盤の安定という最も大切な部分を支える資金として使わせていただきますが、その重要性をしっかりとご理解いただけるようにご説明します。
使途指定のない寄付は基金に積み立て、運用を行います。その基金は、運用益を長期的に教育・研究に活用することで大学の活動に持続可能性を与えるとともに、例えばコロナ禍のように突然危機的状況に陥った場合には、スピード感のある思い切った研究投資に活用することもできます。また、基礎研究など、国の予算がつきにくい分野の発展を支えることもできます。それらの意味でご寄付が大学にとって非常に重要な部分の支えになります。
堺)信頼感の醸成という点でもう少しお話すると、当校の基金は2023年に初のCIO(Chief Investment Officer)を迎えました。世界有数の資産運用会社で投資・運用の責任者を務めた実績を持つ方を運用の責任者に迎えたことで、大学の運用力は格段に上がりました。高額のご寄付をくださる方の中には、その後の運用について気にかけてくださる方も少なくありません。きちんと運用されていることを「見える化」できたことは、寄付者の方々に信頼感や安心感を与えることに繋がったのではないかと考えています。
平野)当校も含め、これまで多くの大学やNPOでは、ある目的のためにご寄付をいただいて、それがなくなったら終わりという形になっていることが多かったです。当校では今、海外の大学を参考に「エンダウメント型財務運営」への移行を進めています。先ほども述べましたが、これは寄付金を元本とし、その運用益で事業を維持することで、必要な財源を半永久的に確保しつつ、社会的な要請に応えたり、大学独自の先行投資を可能にする仕組みです。
東京大学に使途一任という形でご寄付をいただくと、そのお金と想いが半永久的に研究や日本の教育、よりよい世界の実現のために使われていきます。遺贈寄付という生きた証を受け取らせていただくにあたり、これからもご信頼いただける取り組みを模索していきたいと考えています。
3. 遺贈寄付に興味を持っている方へのメッセージ
___最後に、遺贈寄付にご興味をお持ちの方へのメッセージをお願いします。
堺)大学とNPOへの寄付の意義の違いについて少しお話しさせてください。NPOの取り組みは、主に目の前の課題に対してアプローチしていくものだと思います。一方で、社会課題を生み出さないようにするためにはどうすればいいかという観点で、社会課題に立ち向かうことができるのが大学の役割です。社会課題解決における大学とNPOの役割は、車の両輪のようなものと言えます。
目の前のことをケアする人も、その問題がなくなるように根本解決を目指す人も、どちらも大切です。ご自身の興味関心に合わせて一番納得感のある寄付先を決めていただきたいと思います。社会の中での大学の役割を知っていただき、その上で大学を選んでいただけたら、私たちとしては本当に嬉しく思います。
大学では、日々幅広い研究を行っています。当校であれば、最先端量子論から動物病院の犬や猫のことまで、さまざまな取り組みがあることが強みの一つです。興味関心が広く、なかなかこれと定まらない場合は、大学に相談していただければ、関心分野に応じたご提案が可能です。さらに私たちの強みとして、遠い先の未来も大学自体がなくなることはないという点です。遺贈寄付は未来に託すものだからこそ、なくなる心配のない安心感を持っていただけることも大切ではないかと考えています。
平野)遺贈寄付は大きな額ではないとできない、ということはまったくないので、お気軽にご相談いただければと思います。遺贈寄付は、ご自身の人生を楽しみ尽くした後にできる人生最期の社会貢献です。残された財産を未来に託し、未来の社会にバトンを渡す行為でもあります。大学は学生を育て、今はまだない技術や知を生み出し、未来を育てている機関の一つです。未来を託すには非常に親和性の高い寄付先ではないかと思いますので、多くの方に大学への遺贈寄付に関心を持っていただけたら嬉しいですね。
一定額以上のご寄付をいただいた方には、当校の安田講堂に寄付者のお名前を銘板に記す形で謝意を表しています。ご自身が生きた証が、安田講堂で当校とともに時を刻み続けていくことができるのです。少しでもご関心をお持ちいただけましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
4.寄付の使い道について
みなさまからいただいたご寄付は東京大学基金の柱として積み立て、運用原資として活用させていただくとともに、寄付の目的に沿って、それぞれ研究や取り組みの支援に充てさせていただきます。
【寄付使途の例】UTokyo NEXT150
東京大学は2027年に創設150周年を迎えます。この150年に渡る知の蓄積を次の150年につなげて行きたいと考え、東京大学に一任いただくご寄付にUTokyo NEXT150という名称を付しました。平時は東京大学の財政基盤として蓄積され、その運用益とともに、本学の自律的で創造的な教育研究活動に充てられます。そして、社会に必要とされる時に、即時利用可能な財源として機能します。みなさまのご遺志を、よりよい社会に貢献する大学づくりに反映していきたいと考えています。
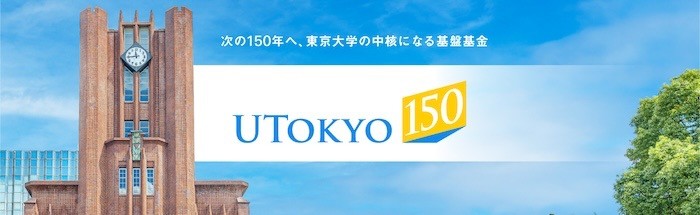
【寄付使途の例】動物医療センター未来基金(VMC基金)
動物医療センターは、家族のように大切な伴侶動物の高度診療を通じて、人と動物の幸せな関係を構築し、人々の平穏と健康を支援しています。全国から研修医を受け入れることで各地の動物医療の発展に貢献し、また、優れた技能と人間性を兼ね備えた次世代の獣医師の教育・育成機関として世界から期待されています。みなさまのご支援で、獣医師の教育と育成をはじめ、動物にも飼い主さまにもやさしい診療施設の整備や、動物に負担の少ない診断・治療を実現したいと考えています。
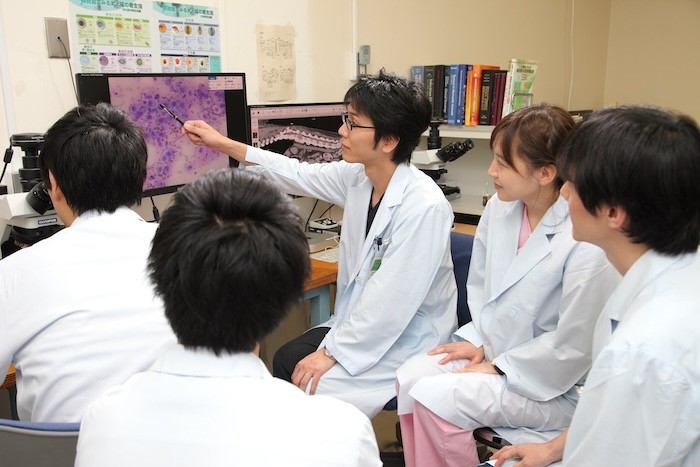
遺贈寄付に関するお問い合わせ窓口(東京大学基金事務所)
TEL:03-5841-1217(10:00~12:00 13:00~16:00 土日祝除く)
フォームからのお問い合わせはこちら
5.団体紹介

・団体名
国立大学法人 東京大学
・所在地
東京都文京区本郷 7-3-1
・代表者
総長 藤井 輝夫
・設立年
1877年(東京大学基金設立は2004年)
・スローガン
志ある卓越。