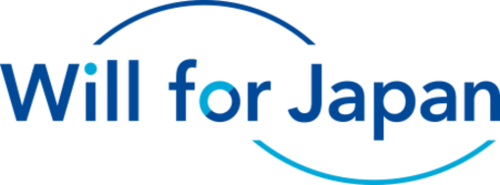遺贈寄付で、貧困や紛争に直面する子どもたちに教育と命を守る支援を/ワールド・ビジョン・ジャパン

認定特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン
ワールド・ビジョンは、キリスト教精神に基づいて世界100カ国で活動する世界最大級の国際NGOです。開発援助、緊急人道支援、アドボカシー(市民社会や政府への働きかけ)を活動の柱として、世界の子どもたちの命と尊厳を守ってきました。創設から70年以上が経ったいま、世界の状況は激変しています。近年では、貧困に加え、紛争や自然災害などの複合的な問題が深刻さを増し、子どもたちはますます厳しい状況に置かれています。「すべての子どもに豊かないのちを」という揺るぎない使命とともに、活動を続けるワールド・ビジョン・ジャパンで、遺贈寄付の担当をされている蘇畑(そばた)光子さんにお話を伺いました。(取材日:2024年6月7日)

蘇畑 光子さん(写真左・帽子の女性)
大学卒業後、2006年にワールド・ビジョン・ジャパン入団。広報、南アジア諸国での支援事業監理等を経て、法人・特別ドナー課で遺贈寄付を担当。
目次:
1. ご本人やご家族の想いを何よりも大切に
___まず、ワールド・ビジョン・ジャパンの位置づけについて教えてください。ワールド・ビジョン全体の中の日本支部という位置づけになるのでしょうか?
ワールド・ビジョンは、現在100カ国で活動していますが、本部、支部という関係はなく、各国事務所が対等なパートナーシップのもとに活動しています。役割を大きく分けると、自国内でファンドレイジングを行う「サポートオフィス」、サポートオフィスからの資金をもとに支援活動を行う「フィールドオフィス」があり、ワールド・ビジョン・ジャパンはサポートオフィスの一つという位置づけになります。
___ワールド・ビジョン・ジャパンが遺贈寄付に本格的に取り組まれたのはいつ頃からですか?
遺贈寄付の取り組みを本格化するという方針が決まったのが、この3年くらいです。2005年頃から、遺贈寄付を受け取ってきた実績がありますが、この5年ぐらいで遺贈寄付に関するご相談をいただく機会が増えてきたと感じています。社会で終活が認知されるようになり、遺贈寄付という言葉自体も少しずつ定着してきたなかで、想いを託したいという方々がいらっしゃり、支援を必要としている子どもたちがいるのであれば、積極的にお受けしていきたいと思っています。
___取り組みを本格化されてからの反響はいかがですか?
そうですね。財産を相続されたご家族からのご寄付が増えている印象です。また、最近では、ご生前中には当団体への寄付歴がない方からのご遺贈が増えてきました。以前は、故人もしくは相続されたご家族が当団体のご支援者というケースがほとんどだったので、そんなところからも、遺贈寄付の広がりを感じています。
___お問合せも増えてきているのですね。大切にされているのはどんなことですか?
遺贈寄付というのは、お金だけでなく、その方の生きてきた証や想いを一緒に受け取らせていただくものだと思っていますので、ご本人や財産を相続されたご家族の想いが実現されることを一番大切にしています。しっかりコミュニケーションをとりながら進めるために、お電話でお話したり、可能であればこちらからお伺いしたり、事務所にお越しいただくなどして、対面でお話をさせていただいています。
ご相談を受けている中で感じることは、当たり前のことですが、一つとして同じケースはないということです。歩まれてきた人生も、現在の状況や相続人の有無なども、本当にお一人おひとりそれぞれです。皆様、色々なことを考え、悩みながら進んでいらっしゃるので、そこに寄り添い、伴走することをこれからも大切にしていきたいと思っています。
2. 「生きた証を見たような気がします」
___特に印象に残っているケースがありましたら教えてください。
当団体のご支援者だった方が、遺贈をしてくださった際のケースです。「子どもたちの教育のために使ってほしい」というご希望があり、ご遺族にもお話を伺い、いくつかの国での教育プロジェクトにご遺贈を使わせていただくことになりました。
そのうちの一つが、アフリカに校舎を建てるというプロジェクトで、ご遺族が現地まで足を運んで、完成した校舎を見てくださいました。ご遺贈で建設した校舎、そしてそこで学ぶ子どもたちの様子を実際に目にして、本当に喜んでくださり、「(亡くなったご家族の)生きた証を見たような気がします」とおっしゃっていたのが心に残りました。

ご本人の遺志を実現することはもちろん大切なことですが、遺贈寄付は悲しみの中にいるご遺族にとって、亡くなられたご家族の“生きた証”が形に残ることで、少しでも悲しみが癒やされたり、前を向くきっかけになるのかもしれない。私たちの活動が、一つの励ましになり得るかもしれない、ということを教えていただきました。
___遺贈寄付があったからこそ成し得たことなどありましたら教えてください。
近年、世界情勢は本当に不安定です。世界各地の紛争、気候変動による影響、頻発する自然災害などによって、日本も含め、世界中で支援のニーズが激増しています。私たちの支援は、もともと、「チャイルド・スポンサーシップ」という地域開発支援から始まっていますが、紛争や自然災害の増加で、長期的な視野に立った支援というよりは、「今すぐ」支援が必要な人たちが急激に増加しています。
そうなると、報道などもそこに集中するので、慢性的な貧困の問題などにはなかなか世界の目が向かなくなってしまいます。遺贈寄付は、光が当たりにくいけれども、継続的な支援が必要とされる人たちの求めに応えていく上で、私たちの活動全体をサポートしていただくための大切な資金となっています。
使途指定がなく、当団体に一任いただいた遺贈寄付の場合は、その時一番支援が必要だと思われるところに集中的に使わせていただいています。もちろん使途の指定がある場合は、ご希望を最大限尊重いたします。
___ホームページには士業の先生や金融機関との連携についても書かれていますね。
そうですね。遺贈寄付の実現には専門的な知識が必要となりますので、遺言や相続に携わる士業の先生や、金融機関などと連携し必要なアドバイスをいただいています。またご要望があれば、ご相談者を紹介することもあります。逆に、こういった方々から遺贈寄付についてのお問合せをいただくことも多いので、ホームページで詳しくご案内しています。まずは、私たちの活動や団体のことを多くの方に知っていただく必要があると思っています。
相続人がいらっしゃらない方などを中心に遺贈寄付のニーズが増えていることを士業の先生からもよくお伺いしますが、ではどこに寄付を託すかというと、そこまで明確な意思をお持ちでない方が多いのが現状のようです。そのギャップを埋めていくためにも、私たちのような受遺団体と士業の先生方、金融機関などの関係者が、少しでも連携や情報共有を深めていくことができればと考えています。
3. 遺贈寄付に興味を持っている方へのメッセージ
___最後に、遺贈寄付へのご興味をお持ちの方へのメッセージをお願いいたします。
遺贈寄付は、その方が一生かけて築いてこられた財産、その方の”生きた証”を託していただくものですので、ご本人、あるいはご遺族のお気持ちを一番大切にさせていただきます。多くの団体さんが遺贈寄付の受け入れをされているので、ご自身の関心やお気持ちにあった選択肢を検討されるとよいのではないかと思います。
実際、複数の団体に分割してご寄付をくださる方も多くいらっしゃいます。その中で、私たちのミッションや活動に共感していただき、当団体に託したいというお気持ちを持っていただけるようであれば、どうぞお気軽にご相談ください。一番お気持ちに添える活動や方法を一緒に検討しながら、お手伝いいたします。
4.寄付の使い道について
皆様からの大切なご寄付は、次世代を担う子どもたちのよりよい未来に、豊かないのちがつながるよう使わせていただきます。ワールド・ビジョン・ジャパンでは「貧困」「教育」「水衛生」「難民」「保健」「災害」など様々な分野での支援が可能です。使途を指定される場合も、使途指定がない場合のいずれにも対応させていただきますので、まずはお気持ちをお聞かせください。
遺贈寄付に関するお問合せ窓口
電話:03-5334-5355(平日10:00~17:00)
フォームからのお問合せはこちら
<遺贈寄付の方法>
・遺贈寄付
・相続財産からの寄付
・特定寄附信託
・お香典やお花料からの寄付
※包括遺贈の受け入れも可能ですが、遺言内容や資産の換価が困難な場合など、お受けできないケースもあります。現金以外の寄付や包括遺贈をご検討の場合は、遺言書作成前にご相談ください。
5.団体紹介

・団体名
認定特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン
・所在地
東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー3階
・代表者
事務局長 木内 真理子
・設立年
1987年(ワールド・ビジョン・ジャパン 設立年)
<ビジョン>
すべての子どもに豊かないのちを
<ミッション>
キリスト教精神に基づく国際的なパートナーであり、イエス・キリストに倣い、貧しく抑圧された人々とともに働き、人々の変革と正義を追求し、平和な社会の実現を目指します。
<活動内容>
1. 特別プロジェクト
「学校を建設したい」「家族で訪れたあの国の子どもを助けたい」など、ご希望やお気持ちを伺い、ふさわしいご支援をカスタムメイドでご提案します。故人やご家族のお名前をプレート等で支援地に残すことも可能です。

2. 緊急人道支援
紛争や自然災害などの人道危機において、国連機関等と連携し、迅速に支援を届けます。特に近年では、難民・避難民の子どもたちの命を守るだけでなく、将来への希望をつなぐ教育支援にも力を入れています。

3. チャイルド・スポンサーシップ
月々4,500円、1日あたり150円の継続支援です。チャイルド・スポンサーになっていただいた方には、支援地域に住む子ども”チャイルド”をご紹介します。ご支援により、子どもを取り巻く環境を改善する長期的な支援活動を実施します。